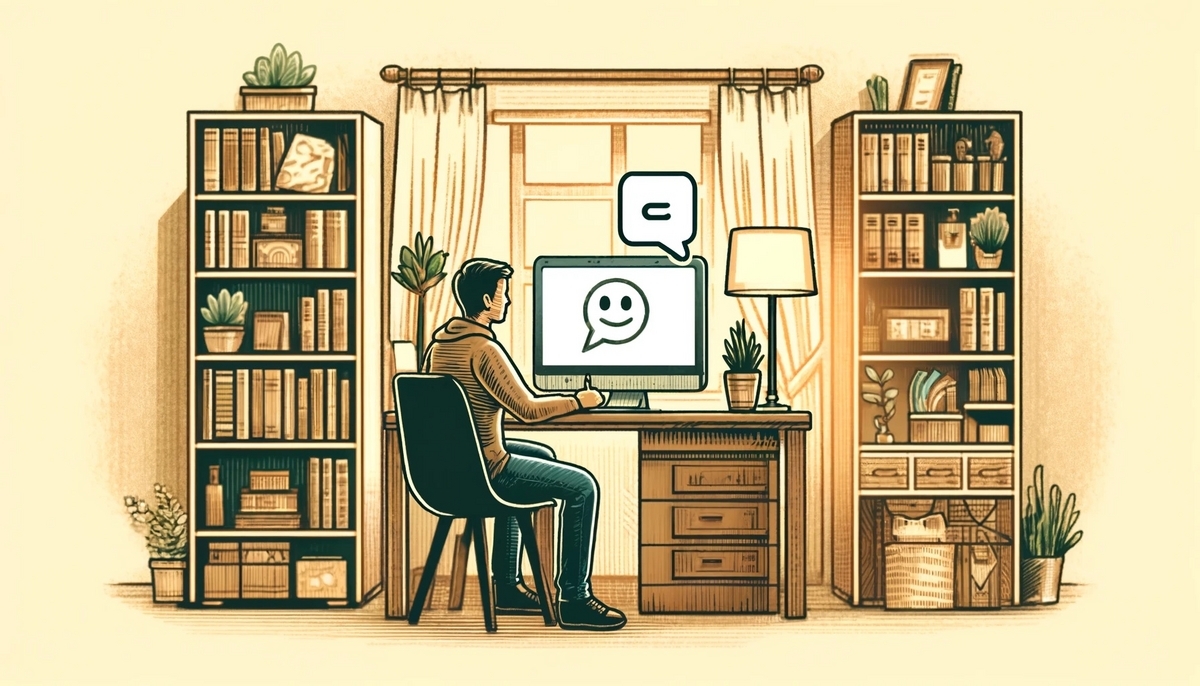
2035年の人間の条件
AI研究者のshi3zさんが「AIが浸透すると人類はネコになる!?暦本vs落合のぶっ飛び対談本」という記事で紹介していた本、暦本先生と落合先生の対談ということで面白そうなので買ってみました。
全体的に面白かったのですが、そのなかで目を引いたのが序盤のこちらの記載。
落合 音声のほうが速いですね。最近は展覧会の計画を立てるときも、チャットGPTのアプリに向かって喋りながら会場を歩いて回るんですよ。「最初の部屋の左には○○を置いて、その先は××にしようかな」とか何とかブツブツ喋る。帰ってきてヒュッとやると、だいたい展示計画ができているわけです。
「ヒュッとやるって何!?」と思ったのですが、ChatGPTとおしゃべりした内容をドキュメントにするっていうのは結構便利そうで面白そうなのでやってみました。
ChatGPTに書籍の感想をインタビューしてもらう
せっかくなので、この本の感想についてChatGPTにインタビューしてもらって、話した内容をヒュッとやる(まとめる)ことにしました。プロンプトは以下みたいな感じです。
- 音声でユーザーとインタビューして、その内容をブログ化します。 - ユーザーと特定の話題に対しておしゃべりしてください。感想をいったり、質問したりしてください。 - ユーザーから要望があったら、インタビューの内容をまとめてマークダウン方式で出力してください。
GPTsにもしてみました。
なお、iPhoneアプリのChatGPTで、音声認識を使って会話して使用することが前提の使い方です。
ChatGPTのインタビュー内容まとめ
以下は、ChatGPTとしばらくおしゃべりしたあとにまとめた内容です。1部の誤記を手直ししましたが、ほぼChatGPTの出力そのままです。悪くはないですが、ちょっとかたいですし、若干面白みにかけますね。
本を知ったきっかけ
「2035年の人間の条件」という本を知ったきっかけは、AI研究者のshi3zさんの「AIが浸透すると人類はネコになる!?暦本vs落合のぶっ飛び対談本」という記事です。著者である落合陽一先生と暦本純一先生の名前を知っていたため、興味を持って購入しました。両先生はコンピューターサイエンスやアート、ヒューマンインタラクションに関心を持つ方々です。
音声認識の利用
本の中で音声認識を使って文章を書く方法が紹介されており、落合先生が展覧会の計画をChatGPTに向かって話しながら進める様子が描かれていました。これに影響を受け、私も音声認識を使ってブログを書こうと試しています。現時点では、騒がしい場所では音声認識が難しいという課題がありますが、静かな環境ではアイデアをすぐに記録できるという利点を感じています。
AIと産業革命の類似点
本の中で、AIの発展が産業革命時の蒸気機関の技術と似ているという話がありました。ジェームズ・ワットが蒸気機関を改良して普及させたように、AIも技術的な進歩を経て現在の隆盛に至っています。人工ニューラルネットワークも一時期「冬の時代」を迎えましたが、技術の進化により再び注目を集めています。このような歴史の類似点がとても面白いと感じました。
AIのキラーアプリ
蒸気機関が船舶の動力源として大きな価値を持ったように、AIにもキラーアプリの存在が重要です。現時点で、チャット型AIがその役割を果たしているかもしれませんが、今後さらに革新的な使い方が出てくる可能性に大きな興味があります。例えば、医療や教育、環境問題など、特定の分野でのAIの活躍が期待されます。
ChatGPTのインタビュー内容の会話形式まとめ
別パターンとして、会話形式のまままとめたものです。プロンプトは「会話形式で文章をまとめてください」とするだけです。
AI: 「2035年の人間の条件」という本についてお話ししたいと思います。まず、この本をどのようにして知ったのですか?また、何があなたの興味を引いたのでしょうか?
からあげ: AI研究者のshi3zさんの「AIが浸透すると人類はネコになる!?暦本vs落合のぶっ飛び対談本」という記事で知りました。作者が落合陽一先生と暦本純一先生という、両方ともよく知っている方だったので、本を買ってみました。
AI: なるほど、知っている著者だったから購入されたのですね。落合陽一先生と暦本純一先生はどのような分野で有名な方々ですか?また、この本のどの部分が特に印象に残っていますか?
からあげ: 二人ともコンピューターサイエンスとか、アートとか、ヒューマンインタラクションとか、そういったところに関心のある方だと思っています。本の中で、音声認識で文章を書くとか、ドキュメントを書くみたいなものがあったので、ちょっと一回やってみようかなと思って、今回も音声認識を試してブログを書こうとしています。
AI: それはとても興味深いですね。音声認識で文章を書くというのは、効率的で新しい表現方法ですよね。この本の中で、音声認識に関するどのような具体的な内容がありましたか?また、実際に試してみてどう感じていますか?
からあげ: 落合先生が展覧会の計画を立てるときに、ChatGPTに向かって歩きながら会場を歩いて回ったりして、展覧会の計画をいろいろおしゃべりして、帰ってきてシュッとやると展示計画ができるみたいなことを言っていたので、ちょっと私も真似してみようかなと思っています。今やってみているので、最後どうなるかが楽しみです。
AI: なるほど、落合先生が展覧会の計画を音声認識で進めているというのはとても面白いですね。実際に試してみて、今のところどう感じていますか?音声認識で文章を書くことで、特に良い点や改善したい点はありますか?
からあげ: そうですね、場所が限られるかなとは思ったりします。
AI: 場所が限られるというのは、例えば騒がしい場所だと音声認識が難しかったりするということですか?それとも、別の理由がありますか?
からあげ: 騒がしいからとか、そういう理由ですね。
AI: やはり騒がしい場所だと認識が難しくなることがありますね。でも、静かな環境で使うと、アイデアをすぐに記録できるので便利ですよね。これからも試していく中で、どんな工夫ができそうだと思いますか?
からあげ: いろんな工夫はできるかなと思います。ちょっと別の話題にしてみようと思うんですけれども、本の中でAIと産業革命の蒸気機関の技術に似ているという話があって、それが面白いなと思います。
AI: それは興味深いですね。AIの発展が産業革命の蒸気機関と似ているというのは、どのような点でそう言えるのでしょうか?具体的にどんな内容が書かれていましたか?
からあげ: 蒸気機関を発明したのはジェームズ・ワットさんなんですけれども、これも最初は性能が出なくて、全然普及していなかったのを半世紀後ぐらいに改良して性能を劇的に向上させたんです。AIも結構同じような歴史を辿っていて、人工ニューラルネットワークも一時期「冬の時代」と呼ばれる停滞期がありましたが、様々な技術の発展で再び盛り返しているところが類似していて面白いなと思います。
AI: なるほど、技術の進化と普及の過程が似ているということですね。ジェームズ・ワットの蒸気機関が改良されて大きな影響を与えたように、AIも技術的な進歩で大きく成長してきたわけですね。AIの「冬の時代」から今の発展に至るまでの過程を振り返ると、確かに共通点が多いですね。現在のAI技術のどの部分が特に興味深いと感じますか?
からあげ: 今のAI技術の興味深さというより、キラーアプリが重要かなと思っていまして、蒸気機関が船舶の動力源として使われることで非常に価値が高まったように、AIにおいてもキラーアプリの存在が重要です。現時点でチャット型AIがその役割を果たしているかもしれませんが、今後もっとすごい使い方が出てくるかが楽しみです。例えば、医療や教育、環境問題など、特定の分野でのAIの活躍が期待されます。
AI: キラーアプリの視点はとても重要ですね。蒸気機関がさまざまな分野で革命を起こしたように、AIもその可能性を秘めています。これからさらにどんな革新的な使い方が出てくるのか、非常に興味深いです。今日はお話を聞かせていただき、ありがとうございました。
まとめ
書籍の感想にChatGPTの音声認識を活用してみたという話でした。今まで音声認識でブログ書くのは、何度も挫折していたのですが、こうやってインタビュー形式でAIとおしゃべりするというのは、結構やりやすい気がします。
本の感想とかは、読むときに気になった箇所をハイライト(マーキング)しておいて、その内容を中心にAIとおしゃべりすれば手軽に書籍の感想ブログが作れそうですね。なかなか本の感想とか書けない人はお試しあれ。
紹介した本
こんな感じに、ChatGPTの便利な活用法を書いている本を出してます!
関連記事
変更履歴
- 2024/06/08 使用方法追記、誤記訂正

