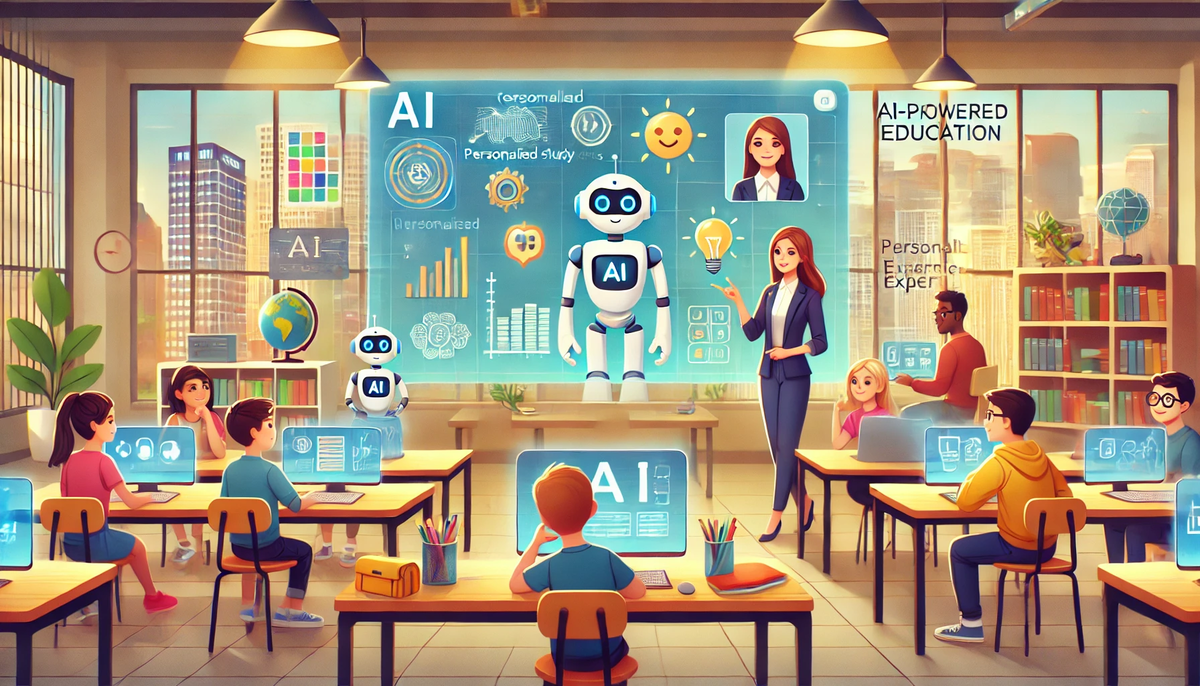
生成AIと教育
生成AI(LLM)、が教育に与える影響に関して以下のツイートしたら、結構反応あったのでもう少し深堀りしたいと思います。
LLMが教育に与える影響に関しては、最近考えることが多いです。
— からあげ (@karaage0703) 2025年2月1日
1番のメリットは、難易度調整ができることな気がしてます。学習の大きなハードルの一つに、自分にとって適切な難易度で分かりやすい教材がないことがあると思いますが、LLMはいくらでも個人に合わせて生成できる
個人的には、学習で詰まるときって、自分のレベルに合う適切な教材がないときが結構あると思っています。自分にあった教材を見つけて、ぐっと理解が進んだ体験は多くの人があるのではないでしょうか?生成AIだと、適切な難易度の教材を生成したり、何度でも解説を要求したり、その解説も、自分にとって分かりやすい説明をしてくれたりと至れり尽くせりです。
最近、良いなと思った使い方として、LLMに例え話をさせるというものがあります。例えば、ガンダムが好きだったら「LightGBMをガンダムに例えて説明してください」といった無茶な要求にも答えてくれます。「ガンダムに例えないでください」と言われたらエヴァンゲリオンでも大丈夫です。何が大丈夫なのかは分かりませんが。
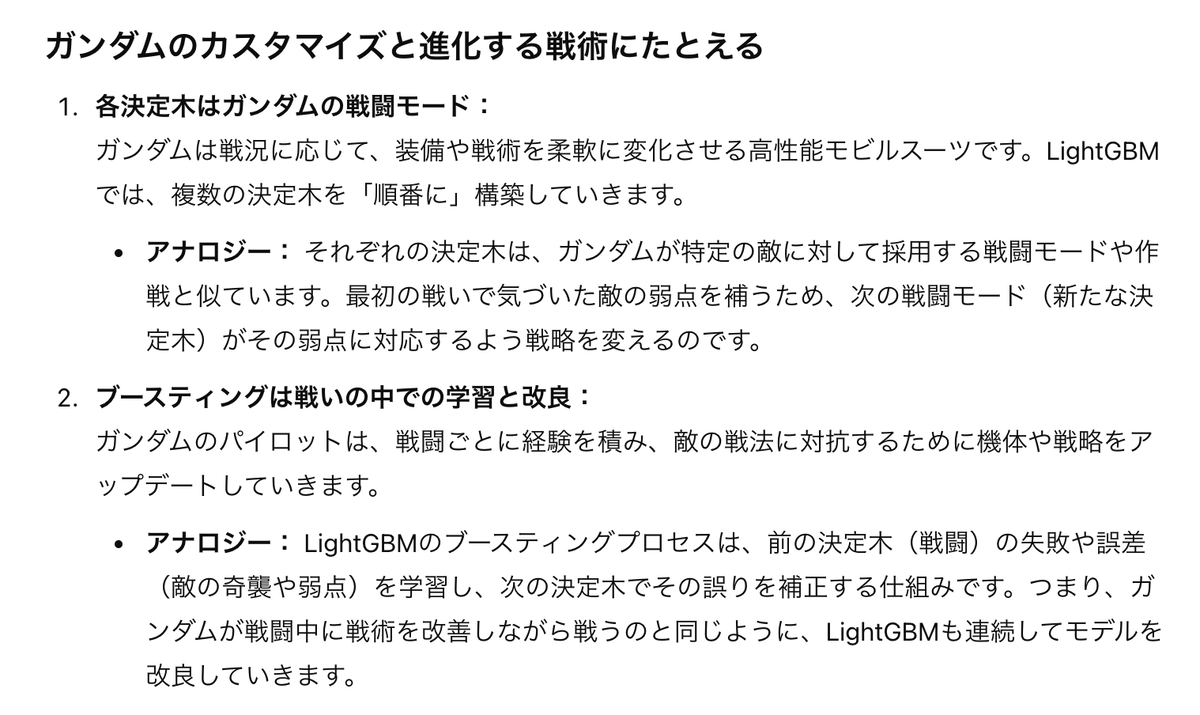
「生成AIに頼って、自分で考えなくなるのでは?」という指摘はありそうですが、多分そうなるのでしょう。電卓が出て、多くの人が自分で(複雑な)計算をしなくなったように、生成AIにより多くの人が複雑な思考を手放すのではないかと思います。もちろん、1部の人は自分で考えると思います。今でも算盤の達人がいるのと同じですね。よりレアな存在になるのだと思います。
それでよいことなのか、悪いことなのかは、正直よく分かりません。全体の傾向としては、そうなるだろうなという単なる予想です。
AIによる教育の具体例
実際にどう教育が変わるのか?という具体例としては、以下の本が面白かったです。
本を読むのはちょっと…という人は、以下の作者へのインタビュー記事で書籍の概要に触れているので、こちらを参照ください。
ざっくり言えば、ChatGPTを活用して100日間毎日アプリを作り続けてプログラミングを学んだという話です。ただ、本を読むと1日10時間くらいプログラミングしていたと書いてあり、これはこれで誰しもができるようなことでは無さそうだな(多分かなり特殊な例)とは感じました。ただ、この著者は、AIがあったからプログラムを書けるようになったのは間違いないと思いますし、それだけで価値があることかなと思います。
この方法論を洗練していったら、より多くの人がプログラムを書けるようになるのか、AIの進化によって、プロンプト1発で何でも出てきて、そもそも学習という概念が崩壊するのかは分からないですが、AIが遥か高みにいっている将棋でも学び続ける人は学ぶので、結局今と同じで、やる人はやるしやらない人はやらないのではないかなと予想しています(割合は変わると思いますが)。ともかく、学習が一つ新しいフェーズに入ったとは言える気がします。
参考までですが、以下の記事は、情報系大学教員(福岡)の立場で、「100日チャレンジ」書籍の感想と教育についての考えが書かれていて面白かったです。
また、自分の子どもの頃は、プログラミングを学ぶと行ったら写経だったのですが、以下の記事でも写経の功罪に触れた後、生成AIの可能性についても言及していて興味深かったです。
まとめ
生成AIが教育について与える影響について、思ったことをとりとめもなく書いてみました。大学までの教育は(受験がなかなか変えれないので)、そこまで大きく変わらないかもですが、大学以降の教育・自己学習においては、待ったなしの状況な気がします。
将棋や囲碁だと、既にAIは人間の遥か高みに達していて、現代の棋士はAIに教えを請うているような状態です。今までは、AIが人間を超えているのは、将棋や囲碁など限られた世界での話でしたが、それがいよいよビジネスなどの実世界にも広がってきているなと感じます。なお、余談ですが、最新刊で人間がAIとガチバトルをしている龍と苺という将棋漫画があって、これはこれで面白いです。
AIが遥か高みに達してしまうと、AIに従って生きれば幸せなのかもしれませんが、そういう世界になるには、まだしばらく時間がかかりそうですし、ただAIに従って生きるだけにならないためにも、自分の学びに生成AI(LLM)を活用する方法を考えてみるのは、よいのではないかなと思います。
記事中で紹介した「100日チャレンジ」の書籍の他、まずは生成AIを知りたいという方は…ぜひ「教えて!からあげ先生 はじめての生成AI」をよろしくお願いいたします(宣伝です)!

